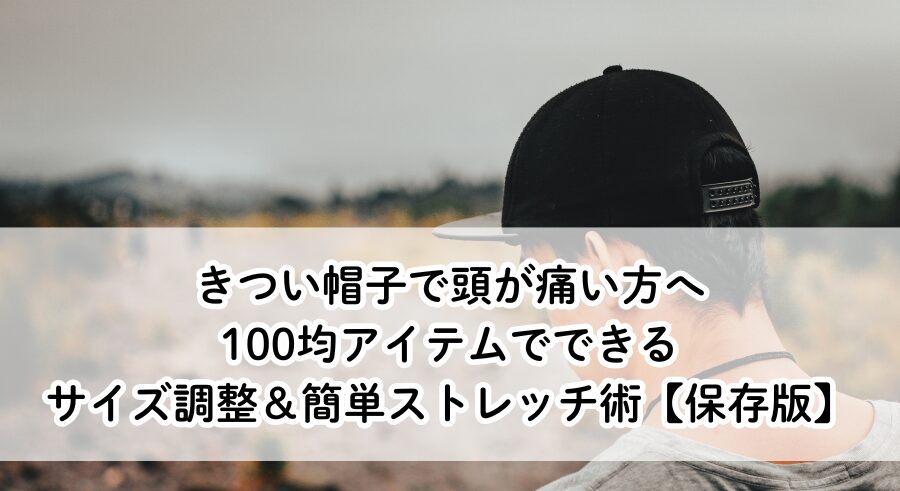きつい帽子で頭が痛い方へ。100均アイテムでできるサイズ調整&簡単ストレッチ術【保存版】
お気に入りのデザインを見つけて購入した帽子。
しかし、いざ長時間かぶってみると、こめかみが締め付けられるように痛くなったり、脱いだ後にくっきりと跡が残ってしまったり。
そんな経験はありませんか?
デザインは好きなのに、サイズが合わないからという理由だけで、クローゼットに眠らせてしまうのは非常にもったいないことです。
実は、少しきついと感じる帽子であれば、ご家庭にある身近なアイテムや、ちょっとした工夫で快適なサイズに調整できる可能性があります。
この記事では、100円ショップで手に入るものを活用した手軽な方法から、専用の道具を使った本格的なストレッチ術、さらには道具がなくても今すぐ試せる裏ワザまで、幅広くご紹介します。
もうサイズで失敗したくない、という方のために、正しい頭のサイズの測り方についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
あなたの大切な帽子が、再びお気に入りの一つとして活躍するお手伝いができれば幸いです。
なぜ?お気に入りの帽子がきつくなる主な原因

買ったときから微妙に小さい
お店での短い試着では気づかなかったけれど、実は購入したときから頭のサイズに合っていなかった、というケースは少なくありません。
特に、オンライン通販での購入や、プレゼントでもらった帽子などは、試着ができないためサイズが合いにくい傾向があります。
人の頭の形は千差万別で、同じ「Mサイズ」という表記であっても、メーカーや帽子のデザインによって実際のフィット感は大きく異なります。
最初は良くても、長時間かぶっているうちに圧迫感を感じてくる、というのもこのパターンに当てはまることが多いでしょう。
ほんの少しのサイズの違いが、後々の快適さに大きく影響してしまうのです。
洗濯による縮み
帽子も衣類と同じように、洗濯によって縮んでしまうことがあります。
特にコットンやウール、リネンといった天然素材は、水分を含むと繊維が膨らみ、乾燥する過程で目が詰まって縮みやすい性質を持っています。
良かれと思ってきれいにした結果、かえってサイズがきつくなってしまった、というのは非常に残念なことです。
これを防ぐためには、洗濯前に必ず帽子の内側についている洗濯表示タグを確認し、指示に従うことが重要になります。
手洗いが推奨されているものを洗濯機で洗ってしまったり、乾燥機の使用が不可のものをうっかり使ってしまったりすると、大幅な縮みの原因となるため注意が必要です。
汗や湿気による素材の変化(特に天然素材)
洗濯をしていなくても、帽子は汗や空気中の湿気を吸収しています。
特に、夏場にかく汗には塩分や皮脂が含まれており、これらが繊維に付着したまま乾燥と吸収を繰り返すことで、素材が硬化したり、わずかに縮んだりすることがあります。
天然素材でできたストローハット(麦わら帽子)やフェルトハットなどは、この影響を受けやすい代表例です。
湿気を含んで柔らかくなった状態から、乾燥して硬くなる過程で、元の形よりも少しだけ小さく変形してしまうのです。
日々の使用で少しずつ変化が進むため、久しぶりにかぶってみたらきつくなっていた、と感じる原因の一つになっています。
【結論】100均に「帽子を大きくする」専用アイテムはある?

残念ながら「大きくする専用品」の取扱いはほぼ無し
結論から言うと、現在のところ、ほとんどの100円ショップでは「帽子を大きくする」という目的のためだけに作られた専用の道具は販売されていません。
探してみると、収納用品や便利グッズなど、多種多様なアイテムが見つかりますが、帽子のサイズを広げるための専門品は見つけるのが難しいのが現状です。
おそらく、その需要が比較的限られているため、定番商品として置くには至っていないのかもしれません。
そのため、100円ショップで帽子のサイズ調整を考えた場合、何か別の商品を工夫して使う「代用」という形が基本になります。
主流は逆の「サイズを小さくする」調整テープ
一方で、100円ショップの帽子売り場や手芸コーナーなどでよく見かけるのは、「サイズを小さくする」ためのアイテムです。
具体的には、帽子の内側にあるスベリ(汗止め)の部分に貼り付ける、クッション性のあるテープが主流となっています。
これは、少し大きめの帽子を購入した場合や、使っているうちに馴染んで緩くなってきた帽子を、頭にぴったりフィットさせるために使われます。
「大きいものを小さくする」という需要の方が一般的であるため、こちらは商品として広く普及しているようです。
帽子を大きくしたい、と考えている方にとっては、少し残念な状況かもしれません。
でも大丈夫!「大きくする」ために使える“代用品”は豊富にある
専用品がないからといって、がっかりする必要はありません。
視点を少し変えれば、100円ショップに並んでいるたくさんの日用品の中に、帽子を大きくするために活用できるアイテムはたくさん隠れています。
例えば、本来は全く別の用途で使われる建築資材や梱包用品などが、帽子のストレッチャー(拡張器)として見事に役立ってくれるのです。
少しのアイデアと工夫次第で、コストをかけずにきつい帽子の悩みを解決できる可能性は十分にあります。
次の項目からは、具体的にどのようなアイテムが使えるのか、そしてその使い方を詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
【100均アイテム編】身近なものでできる!帽子の伸ばし方・広げ方

代用テク①:定番の「すきまテープ」でじんわり広げる
ドアや窓の隙間を埋めて、すきま風や音漏れを防ぐために使われる「すきまテープ」。
実はこれが、帽子を内側からじんわりと広げるのに役立ちます。
方法はとても簡単で、このすきまテープを帽子の内側、額が当たるスベリ(汗止め)の部分に沿って貼り付けるだけです。
テープの厚みが内側から外側へ向かう力を生み出し、時間をかけてゆっくりと生地を伸ばしてくれます。
ポイントは、クッション性のある、少し厚めのタイプを選ぶことです。
一度にたくさん貼るのではなく、まずは一周貼ってみて様子を見ましょう。
まだきついようであれば、その上からもう一周重ねて貼るなどして、少しずつ調整するのが失敗しないコツです。
数日間そのまま放置しておくと、テープの厚みの分だけ帽子が広がってくれます。
代用テク②:梱包用の「エアクッション(プチプチ)」を詰める
荷物を送る際の緩衝材としておなじみのエアクッション、通称「プチプチ」も、帽子のサイズ調整に使える便利なアイテムです。
この方法は物理的に帽子を広げる、非常にシンプルなやり方になります。
まず、エアクッションを大きめに用意し、それを丸めたり畳んだりしながら、帽子の中に隙間なくパンパンに詰めていきます。
まるで帽子が風船のように膨らむくらい、できるだけ固く詰めるのがポイントです。
この状態を保ったまま、数日間から一週間ほど放置しておきます。
エアクッションの持つ張力が、帽子の内側から均等な力を加え続け、生地をゆっくりと伸ばしてくれるのです。
特別な技術は何もいらず、ただ詰めて待つだけなので、誰でも手軽に試すことができるでしょう。
型崩れさせたくない場合は、タオルなどを詰めて形を整えた上に、エアクッションを詰めるとより安心です。
代用テク③:厚紙や段ボールで「自作ストレッチャー」を作る
もう少し本格的に、かつ正確にサイズを広げたい場合は、厚紙や段ボールを使って自分だけの帽子ストレッチャーを作ってしまうという方法があります。
まず、自分の頭周りのサイズを測ります。
次に、そのサイズよりも1cmから2cmほど大きい楕円形を段ボールに描き、カッターなどで切り抜きます。
このとき、段ボールの切り口で帽子を傷つけないよう、縁にテープを巻くなどの処理をしておくと丁寧です。
完成した段ボール製のストレッチャーを、慎重に帽子の中にはめ込みます。
少し抵抗を感じるくらいのサイズ感が理想的です。
この状態で数日間放置すれば、段ボールの形に合わせて帽子が広がってくれます。
楕円の大きさを変えれば、伸ばし具合を微調整できるのがこの方法の大きなメリットです。
少し手間はかかりますが、効果は期待できるでしょう。
【専用アイテム編】確実で簡単!ハットストレッチャーの効果的な使い方

ハットストレッチャーとは?どんな人におすすめ?
ハットストレッチャーは、その名の通り、帽子のサイズを広げるために作られた専用の器具です。
多くは木製またはプラスチック製で、中央にあるハンドルを回すことで、左右に分かれたブロックが外側に広がり、帽子の内側から均等な力を加えて生地を伸ばす仕組みになっています。
100均の代用品と違い、微調整が簡単で、確実に効果を得やすいのが最大のメリットです。
特に、高価なブランド品の帽子や、型崩れさせたくない大切なフェルトハットなどを持っている方には、強くおすすめできるアイテムです。
また、複数の帽子を調整したい方や、これからも帽子を長く愛用していきたいと考えている方にとっても、一つ持っておくと非常に重宝するでしょう。
失敗しない!ハットストレッチャーの選び方とおすすめ3選
ハットストレッチャーを選ぶ際のポイントは、主に「対応サイズ」と「素材」の2つです。
まず、自分の持っている帽子のサイズが、ストレッチャーの調整範囲内に収まっているかを確認しましょう。
S-Mサイズ用、L-XLサイズ用など、いくつかのサイズ展開があるのが一般的です。
素材については、木製のものは湿気を適度に吸収してくれるため、スチームを使ったストレッチとの相性が良いという特徴があります。
一方、プラスチック製のものは手頃な価格で手に入り、手入れが簡単なのが魅力です。
おすすめのタイプを挙げるとすれば、まず一つ目は、幅広いサイズに対応できる汎用性の高い木製タイプ。
そしてもう一つは、初めての方でも気軽に試せるリーズナブルなプラスチック製タイプです。 デザイン性を重視するなら、アンティーク調の木製ストレッチャーも良い選択肢になるでしょう。
基本的な使い方とサイズ調整の目安
ハットストレッチャーの使い方は非常にシンプルです。
まず、ストレッチャーを縮めた状態で帽子の中に挿入します。
次に、中央のハンドルをゆっくりと回していき、ストレッチャーが帽子の内壁に軽く触れるところで止めます。
そこから、さらにハンドルを半回転から一回転ほど回して、生地にテンションをかけます。
この状態で、最低でも24時間、できれば48時間ほど放置します。
焦って一気に広げようとすると、帽子を傷める原因になるため、時間をかけることが重要です。
サイズ調整の目安としては、もとのサイズからプラス1cmから1.5cm程度が限界と考えましょう。
それ以上を目指すと、帽子の本来のシルエットが崩れてしまう可能性があります。
一度で目標のサイズにならない場合は、この作業を数回繰り返してみてください。
アイロンのスチームを併用して効果アップさせる裏ワザ
ハットストレッチャーの効果をさらに高めたい場合、アイロンのスチーム機能を使うのが非常に有効です。
これは、特にフェルトやウールといった天然素材の帽子に効果的な方法です。
まず、前述の通りにハットストレッチャーを帽子にセットします。
次に、アイロンのスチーム機能をオンにし、その蒸気を帽子の内側、特に硬いスベリ(汗止め)の部分にまんべんなく吹きかけます。
このとき、アイロン本体が直接帽子に触れないように十分注意してください。
蒸気によって繊維が湿気を含み、柔らかく伸びやすい状態になります。
その後、ストレッチャーをセットしたままの状態で、帽子が完全に自然乾燥するのを待ちます。
乾く過程で、広がった形のまま繊維が固定されるため、より効果的にサイズを大きくすることができるのです。
【アイテム不要編】今すぐ試せる!道具を使わない最終手段

自分の膝やボールなど丸いものを使って伸ばす
手元に道具が何もない、という状況でも諦める必要はありません。
自分の体の一部や、家にある丸いものを利用して帽子を伸ばす方法があります。
最も手軽なのは、自分の膝頭を使うやり方です。
椅子に座り、膝頭に帽子をぐっと深くかぶせます。
そして、両手で帽子の縁を持ち、前後左右に均等な力でゆっくりと引っ張って伸ばしていきます。
また、サッカーボールやバスケットボールなど、自分の頭より少し大きいサイズのボールに帽子をかぶせて、数日間放置しておくのも有効です。
これらの方法は、力加減が難しく、均等に伸ばさないと型崩れの原因にもなりかねません。
あくまで他の方法が試せない場合の最終手段として捉え、慎重に行うようにしてください。
ドライヤーの熱を利用して馴染ませる(※素材に注意)
ドライヤーの熱を使って、素材を柔らかくして頭に馴染ませるという方法もあります。
ただし、この方法は熱に弱い化学繊維や、接着剤が使われている帽子には絶対に行わないでください。
まず、少しきついと感じる帽子を実際に被ります。
次に、ドライヤーの温風を、帽子の外側から締め付けを感じる部分に当てます。
火傷や素材の傷みを防ぐため、ドライヤーは帽子から15cm以上離し、一箇所に集中させず、常に動かしながら短時間で済ませるのが鉄則です。
全体がほんのり温まったらドライヤーを止め、そのまま帽子が冷めるまで被り続けます。
これにより、素材がご自身の頭の形に合わせて少しだけ伸び、フィット感が向上することがあります。
何度も繰り返しますが、素材の確認は必須であり、慎重に行うべき方法です。
【帽子の種類別】この一手間が大事!素材に合わせた調整のコツ

キャップ(ベースボールキャップ)の場合
カジュアルスタイルの定番であるベースボールキャップは、比較的丈夫なコットンやポリエステル素材で作られていることが多いです。
キャップのサイズ感を左右しているのは、内側にあるスベリ(汗止めバンド)の部分であることがほとんどです。
したがって、このスベリ部分を重点的に伸ばすことを意識すると効果的です。
ハットストレッチャーを使用する場合は、ツバの付け根が歪まないように慎重にセットしましょう。
また、アイロンのスチームをスベリ部分に当ててからストレッチャーを使うと、よりスムーズに伸ばすことができます。
ボールなどに被せておく方法も、型崩れの心配が少なく手軽に試せるのでおすすめです。
ただし、刺繍やワッペンが多いデザインのものは、過度に引っ張ると糸が切れてしまう可能性があるので注意が必要です。
フェルトハット・ウールハットの場合
フェルトやウールでできたハットは、紳士的で上品な印象を与えてくれるアイテムです。
これらの天然素材は、蒸気(スチーム)との相性が非常に良いという特徴があります。
水分と熱を加えることで繊維が柔らかく、形を変えやすくなるのです。
そのため、最もおすすめの方法は、ハットストレッチャーとアイロンのスチームを併用するやり方です。
ストレッチャーでテンションをかけた状態で、内側のスベリを中心にスチームを当て、そのまま完全に乾燥させます。
この方法であれば、型崩れのリスクを最小限に抑えながら、効果的にサイズを広げることが可能です。
高価なものが多いため、少しでも不安がある場合は、無理をせず専門の修理店に相談することも検討しましょう。
ニット帽の場合
伸縮性のあるニット帽は、他の帽子に比べてサイズ調整がしやすいと言えます。
素材そのものを伸ばすというよりは、編み目を広げてゆとりを持たせるイメージです。
最も簡単な方法は、自分の頭より一回り大きいサイズのボールや、丸めたバスタオルなどにニット帽を被せて、数日間放置しておくことです。
物理的に引き伸ばされた状態をキープすることで、編み目が緩み、ゆったりとした被り心地になります。
また、洗濯で縮んでしまった場合には、コンディショナーを少量溶かしたぬるま湯に浸して優しくもみ洗いし、すすいだ後に軽く引っ張りながら形を整えて平干しすると、繊維がほぐれて元のサイズに近づくことがあります。
ストローハット(麦わら帽子)の場合
夏の定番であるストローハットは、非常にデリケートな素材でできています。
乾燥した状態で無理な力を加えると、簡単に繊維が割れたり裂けたりしてしまうため、細心の注意が必要です。
ストローハットを伸ばす際は、必ず少しだけ水分を与えてから作業を行いましょう。
霧吹きを使って、帽子全体、特に内側のスベリ部分を軽く湿らせます。
びしょ濡れにするのではなく、あくまで「しっとり」する程度に留めてください。
素材が少し柔らかくなったら、ハットストレッチャーを挿入し、本当に少しずつ、慎重にハンドルを回して広げていきます。
急激な温度変化も避けるべきなので、ドライヤーなどの熱風を当てるのは絶対にやめましょう。
時間をかけて、ゆっくりと作業するのが成功の鍵です。
失敗しないために!帽子を伸ばす上での共通の注意点
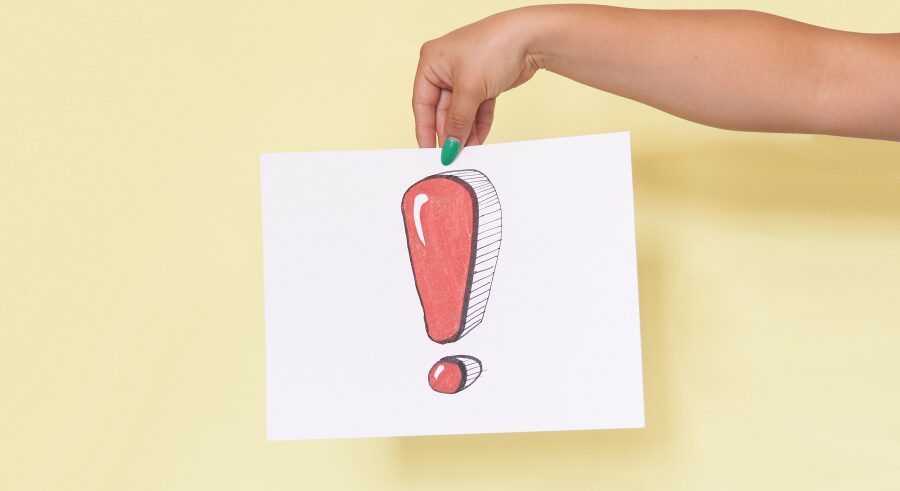
まずは最重要チェック!帽子の「素材」と「洗濯表示」を確認
どのような方法を試すにしても、まず最初に行うべき最も重要なことがあります。
それは、帽子の内側についているタグをしっかりと確認し、「素材」が何であるか、そして「洗濯表示」がどうなっているかを把握することです。
なぜなら、素材によって水や熱に対する耐性が全く異なるからです。
例えば、熱に強い綿素材だと思ってドライヤーを当てたら、実は熱に弱い化学繊維が混紡されていて縮んでしまった、という失敗も起こりえます。
また、「水洗い不可」の表示があるデリケートな素材に、スチームや霧吹きを使うのは非常に高いリスクを伴います。
作業を始める前にこの一手間をかけることが、あなたの大切な帽子を守る上で不可欠です。
「焦りは禁物」が鉄則!ゆっくり、少しずつ力を加える
きつい帽子を早く快適にかぶりたい、という気持ちはよく分かります。
しかし、帽子のサイズ調整において焦りは禁物です。
一度に大きく伸ばそうとして強い力を加えてしまうと、生地が破れたり、縫い目がほつれたり、帽子の美しいシルエットが崩れてしまったりと、取り返しのつかない事態を招きかねません。
ハットストレッチャーを使う場合でも、1日で一気に広げるのではなく、今日はハンドルを半回転、次の日にまた半回転、というように、数日かけるくらいの余裕を持つことが理想です。
ボールに被せるなどの方法でも、長時間かけてじっくりと伸ばすのが基本です。
「ゆっくり、少しずつ」が、帽子を傷めずに成功させるための鉄則だと覚えておきましょう。
水濡れ・熱の加えすぎは変色や型崩れの元
スチームや霧吹きを利用する方法は効果的ですが、水分の量には十分な注意が必要です。
必要以上に濡らしてしまうと、乾くのに時間がかかるだけでなく、シミや色落ち、水垢のような跡が残ってしまう原因になります。
特に、色の濃い帽子や、革などの素材が部分的に使われている場合は慎重に行いましょう。
同様に、ドライヤーなどの熱を使いすぎるのも危険です。
素材そのものを傷めてしまうだけでなく、帽子の形を保つために内部で使われている接着剤(芯材)を溶かしてしまい、型崩れを引き起こす可能性があります。
水分も熱も、あくまで補助的に、「やりすぎない」程度に留めておくことが肝心です。
大切な帽子や高級品はプロへの相談も検討しよう
ここまで様々なセルフケアの方法を紹介してきましたが、もし対象の帽子が、奮発して購入したブランド品であったり、誰かからの贈り物であったり、あるいは特別な思い出の品であったりする場合は、自分で調整する前に一度立ち止まって考えてみてください。
絶対に失敗したくない、という気持ちが少しでもあるのなら、帽子の修理やクリーニングを専門に行っているプロの業者に相談するのが最も賢明な選択です。
プロは、素材や構造に関する深い知識と、専用の高度な機材を持っています。
そのため、帽子の状態を正確に診断し、最も安全で確実な方法でサイズ調整を行ってくれます。
料金はかかりますが、大切な帽子を長く愛用していくための投資と考えれば、その価値は十分にあると言えるでしょう。
【今後のために】もうサイズで失敗しない!正しい頭のサイズの測り方

準備するもの(メジャーなど)
ご自身の正確な頭のサイズを知るために、まずは道具を準備しましょう。
最も適しているのは、手芸用や採寸用として使われる、柔らかい素材でできたメジャーです。
金属製の硬いメジャーや、プラスチックの定規では、頭のカーブに沿わせることができず、正確な数値を測ることができません。
もし柔らかいメジャーが手元にない場合は、伸縮性のない紐やリボン、細長く切った紙などでも代用が可能です。
その紐などを頭に巻きつけ、印をつけたところまでの長さを、後から定規で測れば頭周りのサイズが分かります。
一人で測るのが難しい場合は、誰かに手伝ってもらうとより正確に測れるでしょう。
測る位置はどこがベスト?(眉上と耳の付け根を通るラインなど)
正しいサイズを測るためには、メジャーを当てる位置が非常に重要になります。
一般的に、帽子を被ったときに内側の縁が当たるラインを測るのが基本です。
具体的には、おでこの中央、眉毛の約1cm上の位置からスタートします。
そこから、左右それぞれの耳の付け根の約1cm上を通り、後頭部の一番出っ張っている部分を経由して、スタート地点まで水平にぐるりと一周させます。
この時に測った数値が、あなたの頭周りの基本サイズとなります。
メジャーが斜めになったり、締め付けすぎたり、逆に緩すぎたりしないように注意しながら、鏡を見て確認しつつ測るのがコツです。
何度か測ってみて、最も大きい数値を採用すると間違いがありません。
自分のサイズに合う帽子の選び方のコツ
自分の頭のサイズが分かったら、それを基に帽子を選んでいきましょう。
ここで一つ重要なコツがあります。
それは、測った実寸ぴったりのサイズではなく、少しだけゆとりのあるサイズを選ぶことです。
目安としては、ご自身の頭周りの実寸に対して、プラス0.5cmから1cm程度のサイズ表記の帽子を選ぶのがおすすめです。
ジャストサイズすぎると、長時間被ったときの圧迫感や、髪型の崩れ、脱いだ後におでこに跡がつく原因になります。
少し余裕のあるサイズを選んでおけば、ヘアスタイルを変えた時にも対応できますし、もし少し緩いと感じるようであれば、市販のサイズ調整テープで簡単にフィット感を高めることができます。
「大は小を兼ねる」という考え方が、帽子選びでは有効に働くことが多いのです。
困ったときのQ&A!帽子サイズ調整のよくある質問
- どのくらい大きくできますか?
-
伸ばせる範囲は帽子の素材や作りによって大きく異なりますが、一般的な目安としては、もとのサイズからプラス1cmから、最大でも1.5cm程度が限界と考えておくのが無難です。
数字だけ見ると小さく感じるかもしれませんが、頭周りの1cmは被り心地にかなりの違いをもたらします。
締め付け感がなくなり、快適に感じられるようになることがほとんどです。
これ以上に伸ばそうとすると、帽子のデザインやシルエットが崩れてしまったり、生地や縫製部分に過度な負担がかかって破損の原因になったりするリスクが急激に高まります。
あくまで「微調整」の範囲で行うものと認識しておきましょう - 伸ばしすぎてしまった場合、元に戻せますか?
-
完全に元の状態に戻すのは難しい場合が多いですが、ある程度小さくすることは可能です。
最も簡単で確実な方法は、100円ショップなどでも販売されている「サイズ調整テープ」を帽子の内側のスベリ部分に貼ることです。
テープの厚みの分だけ内径が小さくなり、フィット感を高めることができます。
また、ウールなどの素材であれば、スチームを当ててから乾かす過程で少し縮むこともありますが、これは調整が難しく確実な方法ではありません。
やはり、小さくするよりも大きくする方が難易度が高いため、伸ばす作業は慎重に行い、「伸ばしすぎない」ように注意することが一番大切です。 - 革(レザー)素材の帽子も伸ばせますか?
-
革素材の帽子を伸ばすことは可能ですが、他の素材に比べて難易度は格段に上がります。
自分で行う場合は、革製品専用の「レザーストレッチスプレー」というものと、ハットストレッチャーを併用するのが一般的です。
スプレーを革に吹き付けて柔らかくしてから、ストレッチャーで慎重に伸ばしていきます。
しかし、革は水分や薬品によってシミや硬化、変色を起こしやすい非常にデリケートな素材です。
万が一のことを考えると、基本的には革製品の取り扱いに慣れたプロの修理専門店に任せることを強く推奨します。
もしご自身で試す場合は、必ず目立たない部分でスプレーを試してから、自己責任の上で慎重に行ってください。
まとめ
今回は、きつくなってしまった帽子のサイズを調整する方法について、様々な角度からご紹介しました。
お気に入りの帽子がきつくなる原因は、購入時の見立て違いから、洗濯による縮み、汗や湿気による経年変化まで様々です。
しかし、多くの場合は諦めてしまう必要はありません。
100円ショップで手に入る「すきまテープ」や「エアクッション」などを活用する代用テクニックでも、十分に効果が期待できます。
より確実性を求めるなら、専用の「ハットストレッチャー」を使用するのがおすすめです。
特にスチームと併用することで、その効果を最大限に引き出すことができるでしょう。
どの方法を試すにしても、「素材を確認する」「焦らずゆっくり作業する」「水分や熱を加えすぎない」という3つの注意点を必ず守ることが、失敗を防ぐ鍵となります。
そして何より、今後の帽子選びで後悔しないために、この機会に正しい方法でご自身の頭のサイズを測ってみてください。
この記事が、あなたの帽子ライフをより豊かで快適なものにする一助となれば、これほど嬉しいことはありません。