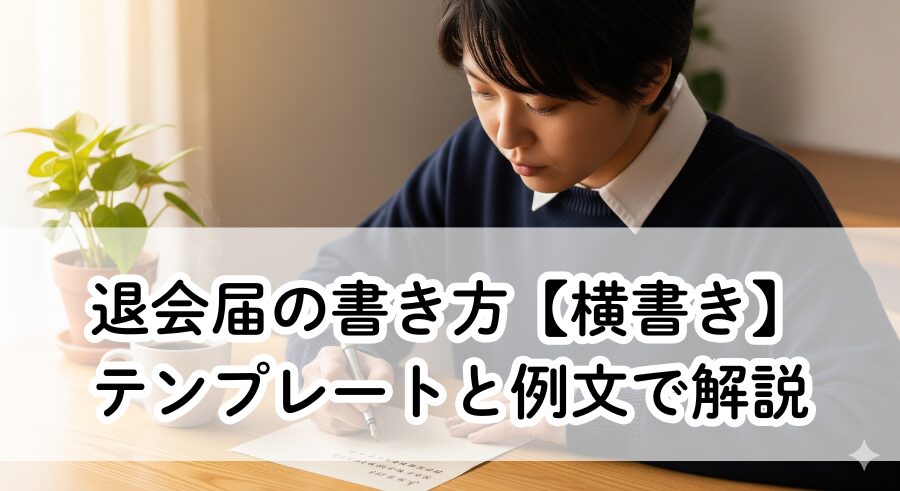退会届の書き方【横書き】テンプレートと例文で解説
習い事やジム、ファンクラブなど、様々なコミュニティに所属していると、いつかは「退会」を考える時が来るかもしれません。
いざ退会届を準備しようとしても、「横書きの場合はどう書けばいいの?」「退会理由は正直に書くべき?」「封筒の書き方にもマナーがあるのかな?」など、次々と疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。
退会は少し気まずいと感じる方もいるかもしれませんが、正しい書き方とマナーを押さえておけば、何も心配することはありません。
この記事では、横書きの退会届に焦点を当て、基本的な書き方から、すぐに使えるテンプレート、状況別の例文までを分かりやすく解説していきます。
封筒の準備や提出時のマナーについても詳しくご紹介しますので、最後まで読めば、きっと安心して退会手続きを進められるはずです。
円満な退会のために、ぜひ参考にしてください。
退会届の基本的な書き方【横書き】

退会届とは?(退職届との違い・提出時期)
退会届とは、あなたが所属している団体やサービスに対して、会員をやめる意思を正式に伝えるための書類です。
例えば、習い事の教室、スポーツジム、学会、ファンクラブなどから抜ける際に提出を求められます。
口頭で伝えるだけでなく、書面として残すことで、「言った」「言わない」といった後のトラブルを防ぐ大切な役割を果たします。
ここで、よく似た言葉に「退職届」がありますが、これは会社を辞める際に提出するもので、退会届とは対象が異なりますので、混同しないようにしましょう。
提出時期については、最も大切なのが所属団体の規約を確認することです。
「退会を希望する月の1ヶ月前までに提出」といったように、多くの場合ルールが定められています。
規約がすぐに見当たらない場合は、受付や事務局に問い合わせてみるのが確実です。
スムーズな手続きのためにも、まずは規定を確認することから始めてください。
横書きの基本構成と必須項目
横書きの退会届を作成する際は、決まった構成と、必ず記載すべき項目があります。
これらを押さえておけば、誰でも簡単に正式な書類を準備できます。
まず、用紙の右上に提出する日付を記入します。
次に、左上には宛名を記載してください。
これは、団体の正式名称と代表者の氏名を書くのが基本です。
代表者名が不明な場合は、「〇〇事務局 御中」としても問題ありません。
宛名の下、少し右側にずらして、ご自身の所属情報(会員番号など)、氏名を書き、名前の下に押印します。
中央には「退会届」と少し大きめの文字で件名を記載しましょう。
本文には、「この度、一身上の都合により、〇〇を退会させていただきたく、お届けいたします。」といった定型文を書き、最後に退会希望日を明記すれば完成です。
これらの必須項目を漏れなく記載することが、円滑な手続きの第一歩となります。
手書きとパソコン作成の選び方
退会届を準備する際、手書きとパソコンのどちらで作成すべきか迷う方もいるかもしれません。
結論から言うと、団体の規定がなければ、どちらの方法でもマナー違反にはあたりません。
それぞれの特徴を理解して、ご自身の状況に合わせて選ぶのが良いでしょう。
手書きのメリットは、なんといっても丁寧な印象を与えられることです。
特にお世話になった先生や指導者がいる習い事などの場合は、手書きの方が気持ちが伝わりやすい側面もあります。
一方で、書き損じた際に一から書き直す手間がかかるのがデメリットです。
これに対してパソコン作成は、修正が簡単で、誰にとっても読みやすい書類が作れるのが大きな利点と言えます。
近年では、事務手続きの効率化の観点から、パソコンでの作成が一般的になりつつあります
もし団体のウェブサイトにテンプレートがあれば、それを利用するのが最も確実な方法です。
【状況別】すぐに使える退会届のテンプレート・例文集

共通で使えるシンプルな横書きテンプレート
ここでは、どのような状況でも使える、基本的な横書きの退会届テンプレートをご紹介します。
退会届の作成に迷ったら、まずはこの形を参考に、ご自身の情報に書き換えてみてください。
パソコンで作成する場合は、これをコピーして編集すると便利です。
手書きの場合も、この構成に沿って書けば間違いありません。
退会理由は、特に伝えたいことがなければ「一身上の都合」で十分です。
最後の挨拶は必須ではありませんが、一言添えることで、より丁寧な印象を与えることができます。
このテンプレートを基本として、次の項目でご紹介する状況別の例文も参考に、あなたに合った退会届を完成させてください。
退会届 〇〇〇〇年〇月〇日 〇〇〇〇(団体名) 代表 〇〇 〇〇 様 (所属部署・会員番号など) (あなたの氏名) 印 この度、一身上の都合により、貴会(またはサービス名)を 退会させていただきたく、ここにお届けいたします。 つきましては、〇〇〇〇年〇月〇日をもって退会とさせて いただきますよう、お願い申し上げます。 これまでお世話になり、誠にありがとうございました。 以上
習い事・ジム向けの例文
ピアノ教室や英会話スクールといった習い事、あるいはフィットネスジムなどを退会する際は、事務的な手続きに加えて、これまでお世話になった感謝の気持ちを伝えると、より円満な退会につながります。
基本的な構成は共通テンプレートと同じですが、本文に少し言葉を添えるのがポイントです。
例えば、「末筆ではございますが、これまでのご指導に心より感謝申し上げます。」といった一文を加えるだけで、印象は大きく変わるでしょう。
特に、個人で運営されている教室などでは、こうした配慮が大切になります。
もちろん、必ず書かなければならないわけではありません。
あくまでご自身の気持ちに合わせて、感謝の言葉を添えるかどうかを判断してください。
以下に例文を記載しますので、参考に調整してみましょう。
【例文】
本文:
私儀、この度、一身上の都合により、〇〇〇〇(ジム名や教室名)を退会させていただきたく、お届けいたします。
〇〇〇〇年〇月〇日をもちまして、退会とさせていただきたく存じます。
短い間ではございましたが、丁寧にご指導いただき、誠にありがとうございました。
貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
協会・学会・ファンクラブ向けの例文
特定の分野の専門家が集う協会や学会、あるいはアーティストなどを応援するファンクラブを退会する場合、手続きは比較的、事務的に進むことが多いです。
そのため、退会届も簡潔で分かりやすい内容を心がけるのが良いでしょう。
これらの団体では、会員一人ひとりを番号で管理していることがほとんどです。
したがって、ご自身の氏名に加えて、会員番号を忘れずに記載することが非常に重要になります。
会員番号が分からないと、本人確認に時間がかかり、手続きが遅れてしまう可能性も考えられます。
会員証や送られてくる会報などで、事前にご自身の会員番号を確認しておきましょう。
退会理由も「一身上の都合」で全く問題ありません。
感謝の言葉を添えるのも丁寧ですが、なくても失礼にはあたりません。
【例文】
所属:会員番号 12345
氏名:〇〇 〇〇
本文:
この度、一身上の都合により、貴会を退会いたします。
つきましては、規約に基づき、〇〇〇〇年〇月〇日をもって退会とさせていただきますので、ご査収のほどよろしくお願い申し上げます。
在籍中は大変お世話になりました。
PTA・自治会向けの例文
PTAや自治会は、地域コミュニティとの関わりが深い組織です。
そのため、退会する際には、今後のご近所付き合いも考慮し、特に丁寧な対応を心がけることが大切です。
退会理由については、「一身上の都合」としても構いませんが、もし差し支えなければ、「転居のため」「家庭の事情により」など、少し具体的に伝えた方が、周囲の理解を得やすい場合があります。
もちろん、詳しく説明する必要はありません。
また、これまで役員として活動してきた場合は、後任者への引き継ぎなどについて、事前に相談しておくと、よりスムーズに退会できます。
他の会員の方々への配慮を忘れず、誠実な姿勢で手続きを進めることが、円満な退会の鍵となります。
【例文】
本文:
私儀、この度、家庭の事情により、PTA(自治会)を退会させていただきたく、お届けいたします。
本来であれば、引き続き活動に貢献すべきところ、誠に申し訳ございません。
末筆ではございますが、皆様の今後のご健勝と、PTA(自治会)の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
退会理由の書き方と伝える際のポイント
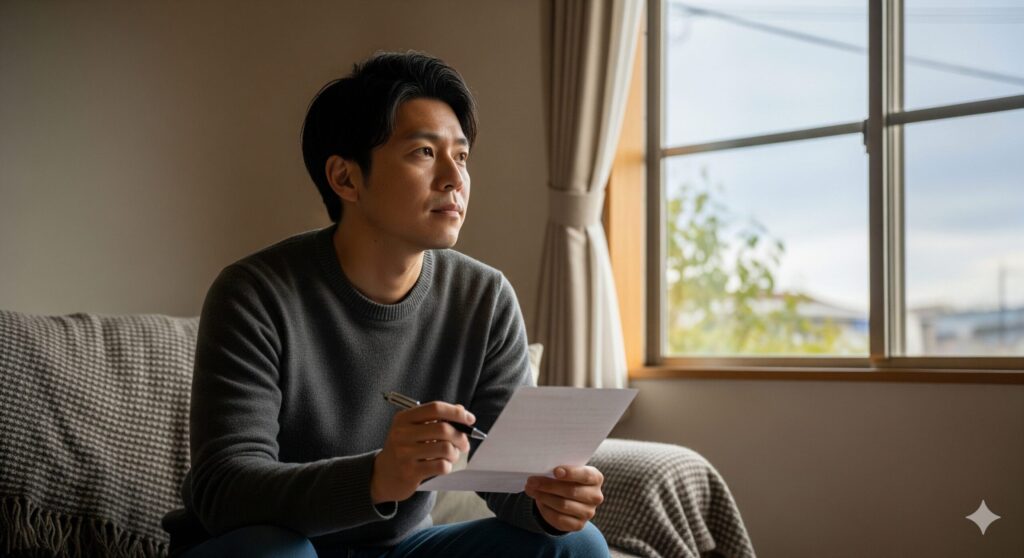
基本は「一身上の都合」で問題ない
退会届を書く上で、多くの方が悩むのが「退会理由」の書き方ではないでしょうか。
しかし、結論から言うと、ほとんどの場合は「一身上の都合により」という定型句で全く問題ありません。
なぜなら、団体側が退会理由を知りたいのは、主に事務手続き上の記録のためであり、個人のプライベートな事情に深く立ち入る意図はないからです。
この「一身上の都合」という言葉は、個人的な理由全般を指す便利な表現です。
これを使うことで、詳しい説明を求められることなく、スムーズに手続きを進められるという利点があります。
もし理由を聞かれても、「家の事情でして」などと、差し障りのない範囲で答えれば十分です。
したがって、退会理由の書き方に迷ったら、まずは「一身上の都合」と記載することを基本として考えて良いでしょう。
具体的な理由を書く場合の例文と注意点
「一身上の都合」では少し事務的すぎると感じる場合や、理由を伝えた方が円満に退会できると考えられる場面もあります。
その際は、簡潔かつ客観的な事実を記載するのがポイントです。
例えば、「転居のため」「仕事の都合により、活動への参加が困難になったため」「家庭の事情により」といった表現がよく使われます。
このように書くことで、相手も状況を理解しやすくなるでしょう。
ここで注意したいのは、あくまで理由は簡潔に伝えるということです。
長々と個人的な状況を説明したり、感情的な文章になったりするのは避けるべきです。
退会届は、あなたの意思を正式に伝えるための公的な書類であるということを念頭に置き、誰が読んでも誤解のない、分かりやすい表現を心がけてください。
避けるべきNG表現
退会届は、円満な関係を保ちながら手続きを終えるための大切な書類です。
そのため、たとえ団体に対して何らかの不満があったとしても、それを退会理由として記載するのは避けるべきです。
例えば、「運営方針に納得できないため」「他の会員との人間関係に疲れたため」といったネガティブな表現は、見る人を不快にさせ、トラブルの原因になりかねません。
このような感情的な内容を書いてしまうと、後味が悪くなるだけでなく、場合によっては退会手続きがスムーズに進まなくなる可能性もあります。
退会届は、あくまで事務手続きのための書類と割り切り、不平不満をぶつける場ではないと理解することが重要です。
もし何か伝えたいことがある場合は、退会届とは別に、信頼できる担当者に直接、穏やかに話す機会を設けるのが賢明な判断と言えるでしょう。
退会届の封筒の書き方と提出マナー
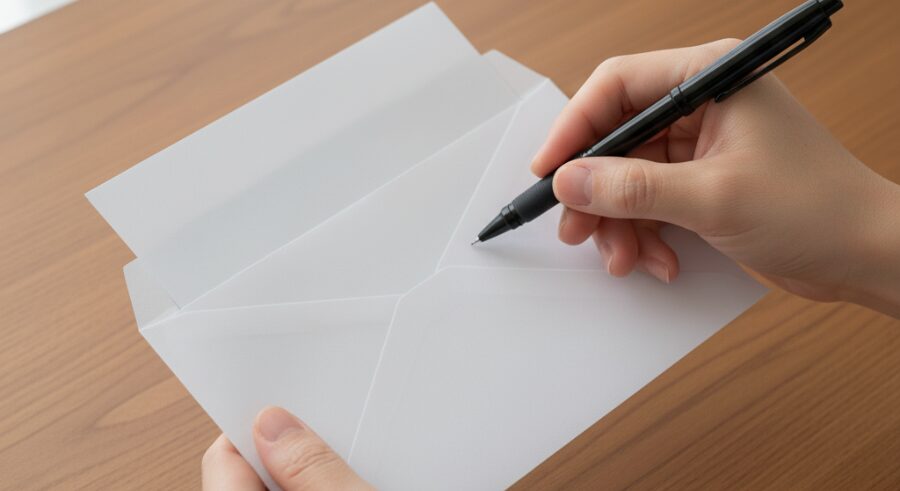
封筒の選び方と宛名の書き方(表面・裏面)
退会届を提出する際は、書類をそのまま渡すのではなく、封筒に入れるのが基本的なマナーです。
封筒は、中身が透けにくい白無地のものを選びましょう。
サイズは、退会届の用紙を三つ折りにしたときに入る「長形3号(長3)」が一般的です。
まず、封筒の表面には、中央に「退会届」と黒のペンで少し大きめに記載します。
こうすることで、他の郵便物と紛れず、重要な書類であることが一目で分かります。
そして、右側に宛先の郵便番号、住所、団体名を、左側には代表者名などを書きます。
団体宛ての場合は「御中」、個人宛ての場合は「様」を使い分けましょう。
次に、裏面です。
左下には、ご自身の郵便番号、住所、氏名を記入します。
封を閉じた後、のり付けした部分に「〆」マークを書くと、より丁寧な印象になります。
封筒の書き方 まとめ
| 表面 | ・中央に「退会届」と記載 ・右側に宛先の郵便番号・住所・団体名 ・左側に代表者名(〇〇様)または団体名(〇〇御中) |
| 裏面 | ・左下に自分の郵便番号・住所・氏名 ・封じ目に「〆」を記載 |
郵送する場合の注意点と添え状の書き方
退会届を郵送で提出する場合は、いくつかの点に注意が必要です。
まず、退会届の用紙は、きれいに三つ折りにします。
折り方は、下から3分の1を折り上げ、次に上から残りをかぶせるように折ると、相手が開いたときにすぐに内容を読み始められます。
郵送方法は、基本的には普通郵便で問題ありません。
ただし、「きちんと届いたか心配」という方は、郵便物の追跡ができる「特定記録郵便」や、受け取りのサインが必要な「簡易書留」を利用すると安心です。
また、郵送の際には、「添え状(送付状)」を同封すると、より丁寧な印象になります。
添え状は必須ではありませんが、誰が、何の書類を送ったのかを明確にする役割があります。
「拝啓」から始まり、簡単な挨拶と、「この度は退会届を一部送付いたしますので、ご査収のほどよろしくお願いいたします。」といった内容、そして「敬具」で締めくくる簡単なもので十分です。
手渡しする場合のマナー
退会届を担当者に直接手渡しする場合は、郵送とは少し異なるマナーがあります。
まず、退会届を入れた封筒ですが、この場合は封をしないのが一般的です。
これは、相手がその場で中身を確認しやすいようにという配慮からです。
もちろん、封筒の表面に宛名などを書く必要もありませんが、「退会届」とだけは記載しておくと親切でしょう。
渡すタイミングも重要です。
相手が忙しくしている時間帯は避け、少し落ち着いた頃を見計らって声をかけるようにしましょう。
そして、渡す際には、「お忙しいところ恐れ入ります。退会届をお持ちいたしましたので、ご確認をお願いいたします。」など、必ず一言添えるのがマナーです。
もしお世話になった方であれば、この時に直接感謝の気持ちを伝えるのも良い機会になります。
最後まで丁寧な対応を心がけることが、円満な退会につながります。
退会届に関するよくある質問

- 退会届はメールや電話で済ませても良い?
-
退会届の提出方法について、メールや電話で代用できないかと考える方もいるでしょう。
この点については、団体のルールによって対応が異なります。
したがって、まずは所属している団体の規約や会則をしっかりと確認することが最も重要です。
規約に「退会時には、所定の書面を提出すること」といった旨の記載があれば、それに従う必要があります。
この場合、メールや電話だけでは正式な手続きとして認められない可能性が高いです。
一方で、最近ではオンラインで完結するサービスやファンクラブなど、ウェブサイトの専用フォームやメールでの退会手続きを正式な方法としているところも増えています。
もし規約を見てもよく分からない場合は、自己判断で進めるのではなく、事務局や担当窓口に問い合わせて、正しい手続きの方法を確認するのが最も確実で安心な方法です。 - 提出後に撤回はできますか?
-
一度提出した退会届を、「やはり続けたい」という気持ちから撤回したいと考えることもあるかもしれません。
しかし、原則として、一度受理された退会届の撤回は非常に難しいと考えた方が良いでしょう。
なぜなら、退会届は「退会する」という明確な意思表示であり、団体側は提出された書類に基づいて、会員情報の削除や月謝の停止といった事務手続きを進めてしまうからです。
手続きが完了した後に撤回を申し出ても、元に戻すのは簡単ではありません。
ただし、まだ担当者が書類を確認しておらず、正式に「受理」される前であれば、相談次第で撤回が認められる可能性はゼロではありません。
いずれにしても、退会届を提出するということは、非常に重い決断です。
後で後悔することがないように、提出する前にもう一度、本当に退会して良いのかをじっくりと考える時間を持つことが大切です。 - 退会届が受理されない時の対処法
-
万が一、正しく作成した退会届を提出したにもかかわらず、正当な理由なく受理されない、あるいは不当な引き止めにあうといったトラブルに遭遇した場合は、冷静に対処することが重要です。
まずは、なぜ受理されないのか、その理由を相手に具体的に確認しましょう。
もしそれが、規約上の手続き不備(例えば、提出時期が早すぎるなど)であれば、ルールに従って再度手続きを行う必要があります。
しかし、理由が曖昧であったり、納得できないものであったりした場合は、次の手段を考える必要があります。
その一つが、「内容証明郵便」を利用して退会届を送付する方法です。
これは、いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に送ったのかを郵便局が証明してくれるサービスです。
法的な証拠能力があるため、受け取った側も無視することはできません。
ただし、これは最終手段であり、相手との関係が悪化する可能性もあります。
できる限り、まずは話し合いによる円満な解決を目指しましょう。
まとめ
今回は、横書きの退会届の書き方について、テンプレートやマナーを交えながら詳しく解説しました。
退会という手続きは、少し気が重いものかもしれませんが、ポイントさえ押さえれば決して難しいものではありません。
まず、所属団体の規約を確認し、定められた手順に従うことが最も大切です。
その上で、この記事でご紹介した基本構成と必須項目に沿って書類を作成しましょう。
退会理由は、基本的には「一身上の都合」で問題なく、団体への不満などネガティブな内容は避けるのが賢明です。
また、手書きでもパソコン作成でもマナー違反にはなりませんが、読みやすさを考えるとパソコンでの作成が便利です。
最後に、封筒の準備や提出時のマナーといった細やかな配慮が、あなたの丁寧な人柄を伝え、円満な退会へと導いてくれます。
この記事が、あなたのスムーズな退会手続きの一助となれば幸いです。